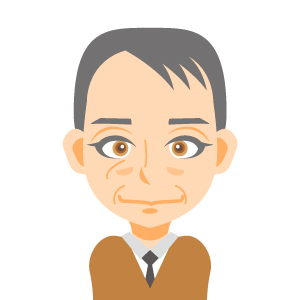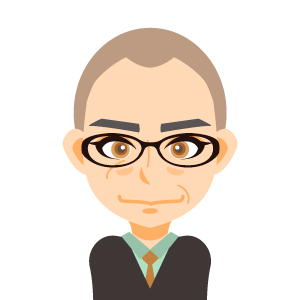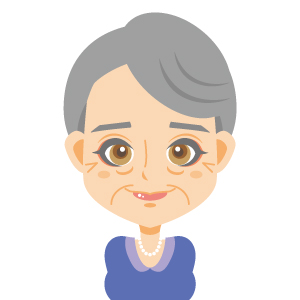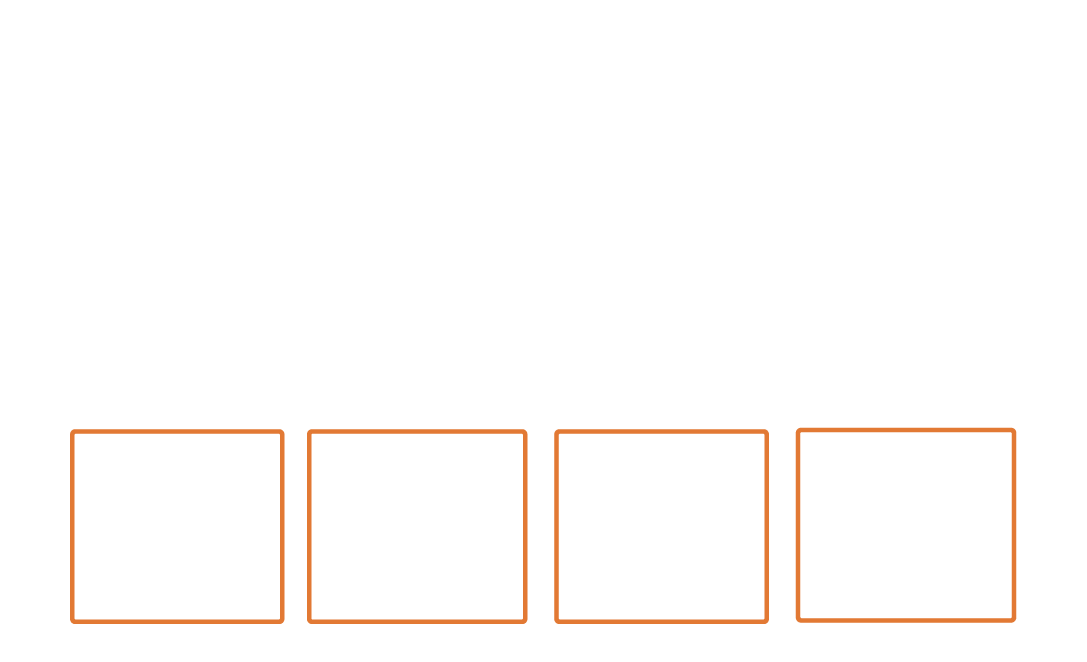塗装専門家相談
閲覧数ランキング
-

ウッドデッキに塗る塗料は水性、油性のどち...
ウッドデッキに塗る塗料は水性、油性のどちらがいいですか? 不格好で...
- 14件の回答
- 閲覧数139584人
-
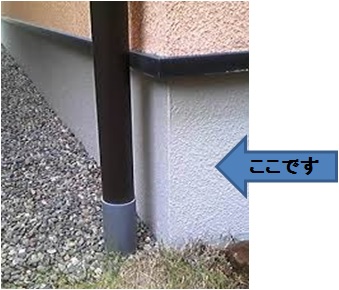
家の基礎?地面近くのコンクリートの所は塗...
どこの家を見ても、 地面に接してる基礎と言う部分ですか?(専門用語...
- 19件の回答
- 閲覧数119629人
-

窓枠(窓廻り)のコーキング打ち替え、増し...
こちらでは、直接塗装店さんが質問に答えて下さるということで、何点か質...
- 12件の回答
- 閲覧数76460人
-

タバコのヤニで汚れた壁紙の塗装はできます...
マンションに住んでいますが、部屋の中の白い壁紙がタバコのヤニで汚れて...
- 21件の回答
- 閲覧数62210人
-

窓ガラスとサッシにはみ出したコーキングの...
窓ガラスとサッシをつなぐシリコンシーリングの部分が長年の結露でカビて...
- 8件の回答
- 閲覧数56712人